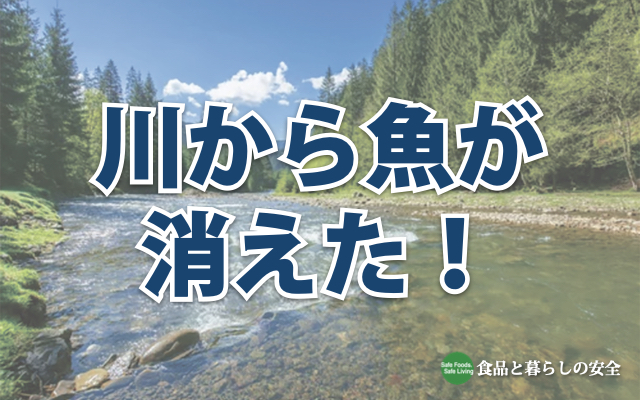肌で感じる減少
「ここ20年ぐらい、魚がずいぶん減ったと肌で感じている。釣り仲間に聞いても、みな同じことを言っている。自分が子どものころは川に湧くように魚がいたのに、今は本当にいなくなった」
こう話すのは、公益財団法人日本釣振興会(日釣振)の常任理事、柏瀬巌さんです。日釣振は「釣りの健全な振興を図る」ことを目的に、一般の釣り人や釣具店・メーカーなどが1970年に設立。柏瀬さん自身も、群馬県太田市で釣具店を営み、子どもの頃から釣りを趣味としてきました。
「減ったというエビデンスはないが、人々が感じる違和感、肌感覚というのは、意外と正確だと思っている」と柏瀬さんは言います。
特に減ったと感じているのが、コイ科のウグイやオイカワ。日本列島の幅広い地域に生息し、釣り人に人気の淡水魚です。ただ、「いわゆる雑魚と呼ばれる種類で、一般にはほとんど関心を持たれないため、いなくなってもニュースにならない」(柏瀬さん)。
このままでは釣りの文化が消滅すると危機感を抱いた日釣振は、プロジェクトチームを立ち上げ、全国各地の会員や専門家の協力も得て犯人捜しに乗り出しました。
魚が減っている原因として考えられるのは、地球温暖化や、開発などに伴う河川環境の変化、外来生物の侵入、乱獲など様々。しかし、ウグイやオイカワの減少が報告された水域を調べたところ、それらが関係している可能性は低いことがわかりました。
例えば、地球温暖化の影響に関しては、海洋においては海水温の上昇などで魚の生息地域が変わるといった事例が報告されていますが、河川においては、特に上・中流域で、地中深くからの湧き水や流速などによって水温の変化はあまり見られませんでした。
河川工事の影響に関しても、今は過去の反省から生態系への影響をできるだけ少なくする対策が講じられています。このため、工事がウグイやオイカワの生息数の激減をもたらしているとは考えにくいとの結論に達しました。
ネオニコチノイド系農薬が浮上
原因究明が難航する中、2019年11月に米国の科学誌「サイエンス」に掲載された、東京
大学大学院の山室真澄教授らのグループによる1本の論文が、プロジェクトチームの目に留まりました。
島根県宍道湖で1993年を境にウナギやワカサギが激減した原因を調べたもので、宍道湖周辺の水田にまかれた殺虫剤のネオニコチノイド系農薬が河川や地下水を経由して湖に流れ込み、その影響でウナギやワカサギのエサとなる動物プランクトンや水生昆虫が減った可能性が高いと指摘しています。
ウグイやオイカワも基本、虫を主食としています。そこで日釣振は、ネオニコチノイド系を含む農薬や化学物質の影響を一番に疑い、詳しい調査に乗り出しました。
2023年には、全国40カ所の河川でネオニコチノイドの濃度を調査。38地点でネオニコチノイドの成分が検出されました。2024年には全国233カ所の河川で同様の調査を行いました。
議員連盟にも要望
魚の減少を可視化するため、全国の釣り人ら約5,000人に対するアンケート調査も2024年に実施。ウグイやオイカワ、カワムツ、オオクチバスなどの釣果がこの5~30年の間にどう変化したか聞いたら、57% が「とても減っている」、28%が「減っている」と答えました。
さらに、農薬と淡水魚の減少との因果関係を明らかにするため、今年から来年にかけて、ネオニコチノイド系農薬を使用している水田とその周辺の河川と、使用していない水田とその周辺の河川との比較調査を、西日本有数の稲作地帯である豊岡市で行う計画です。
独自調査を行う一方で、釣魚議員連盟(麻生太郎会長)と、環境省や農林水産省など関係省庁に要望書を提出し、ネオニコチノイド系農薬対策の強化を訴えています。
もちろん調査にはお金がかかります。柏瀬さんは「そんなものに日釣振のカネをつぎ込んでどうするのか、という批判もたしかにある」と明かします。また、詳しく調査してみたら、ネオニコチノイド系農薬は白だったという可能性もあります。
反対意見や徒労に終わる可能性がありながらも、川魚が釣れなくなった原因を究明しようとするのは、釣り人としての使命感からです。
水俣病の二の舞を心配
日釣振では釣り人のことを「水辺の監視人」と呼んでいます。釣り人は釣果を上げようと常に水辺を観察している。その結果、水辺の異変にいち早く気づき、大問題が起きる前に社会に警鐘を鳴らすことができるから、と柏瀬さんは説明します。
過去の公害事件の中にも、水辺の異変が結果的に予兆となったものがありました。代表が水俣病です。
水俣病公害では、人間の異変がニュースとなる前に、実は、水辺の異変が起きていました。不知火海に魚がプカプカと浮き始めていたのです。しかし、ニュースにはなりませんでした。
その後、水俣では、母親が魚から摂取したメチル水銀が胎盤を通過して胎児に影響を与え、先天性の病気を抱えた子どもがたくさん生まれました。
ネオニコチノイドも、胎盤を通過して胎児の発育に影響を与えることが研究からわかっています。
柏瀬さんは「今起きている淡水魚の減少が、水俣病のように、後に人間に起きるかもしれない大きな問題の予兆とならなければいいが」と心配しています。