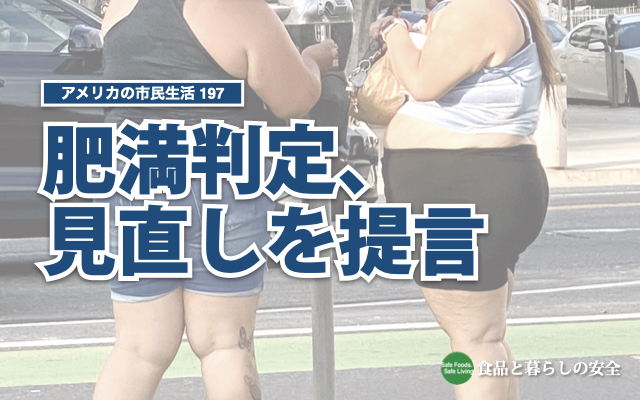B M I は不正確
現在、肥満かどうかの判定にはBMI( ボディー・マス・インデックス)が世界的に採用されています。
BMI は体重(kg)を身長(m)の2乗で割った値。計算方法がシンプルなので誰でも自分の肥満度を簡単に把握できるメリットがある半面、シンプルすぎて肥満が正確に判定されないという問題が、昔から指摘されてきました。
BMI で肥満と判定されても明らかに健康な人は大勢います。
典型がスポーツ選手。アスリートはトレーニングで筋肉が増量し体重が増すため、BMIを適用すると「肥満」と判定される人が少なくありません。
例えば、アメリカ大リーグの大谷翔平選手は、ロサンゼルス・ドジャースの公式サイトによると、身長が193.04センチ、体重95.34キロ。計算すると、BMI は25.585となります。
日本の厚生労働省はBMI が25以上を肥満と定めているので、その基準に照らせば、大谷選手は肥満ということになります。しかし、大谷選手を肥満と思う人はおそらくいないでしょう。
逆に、BMIで見ると肥満でなくても、筋肉量が少なく脂肪が多いいわゆる隠れ肥満も大勢います。隠れ肥満は、肥満が原因の病気にかかるリスクが高いので、これはBMI が意味をなしません。
人種によっても違う
また、BMI に基づく肥満判定はもともとヨーロッパ系の人たちを念頭に開発されたため、アジア系など他人種には当てはまらないとも言われてきました。
世界保健機関(W H O)やアメリカなどの基準ではBMI が30以上で肥満と判定されますが、日本は25以上で肥満とみなしているのは、そうした理由からです。
体が成長途上の子どもも、BMIによる肥満判定は適当ではないと考えられています。
そこで世界中の専門家たちが議論を重ね、肥満の判定方法の見直しを提言しました。
提言に加わったのは、アメリカ、イギリスを中心に、カナダ、メキシコ、ブラジル、フランス、ドイツ、イタリア、オマーン、ナイジェリア、南アフリカ、オーストラリア、シンガポール、中国、韓国、日本など世界二十数カ国の研究機関で働く専門家58人。
今年1月14日、英語のオンライン学術誌「ランセット糖尿病・内分泌学誌」上で発表しました。
肥満を正しく判断
提言はまず、肥満を「過剰な脂肪の蓄積によって体内の組織や臓器、あるいは体全体の機能に変化が生じる慢性の全身性疾患」と定義。
そして、現行のBMIに基づく判定は、体内の脂肪量を過小、あるいは逆に過大に見積もる可能性があるため、適切な治療や効果的な公衆衛生政策の立案を妨げる恐れがある、と指摘しています。
こうしたBMI 判定の欠点を補うため、専門家は、医療従事者や各国の公衆衛生当局に対し、BMI を肥満の最終判定ツールとして使うのではなく、患者を振るい分けるスクリーニングの手段として利用するよう提案しています。
そして、スクリーニングの結果、肥満の疑いのある患者に対してだけ、腹囲を測るなど追加の検査をしたり合併症の有無を調べたりし、患者、医療機関の双方にとって効果的な治療を目指すべきだと述べています。
また、肥満患者を「臨床的肥満」と「前臨床的肥満」の二つのグループに分け、それぞれのグループにあった治療を施すよう提案しています。
臨床的肥満とは、BMI や過脂肪など肥満の指標を満たし、かつ息切れ、股関節や膝の痛み、高血圧、心臓病、腎臓病、糖尿病など肥満に関連する病状が見られ、早急な治療が必要な患者と説明。
これに対し、前臨床的肥満とは、それらの症状はほとんど見られないものの、発症リスクがあるため、予防的対処が必要な患者と定義しています。
日本は、2008年から始まった「特定健診・特定保健指導」で、腹囲や中性脂肪などの値を肥満の診断に取り入れるなど、今回の専門家の提言を一部先取りした形で肥満対策を進めています。
世界的エピデミック
判定方法が議論になるのは、今や世界の多くの国で、肥満問題の解決が公衆衛生上の喫緊の課題となっているからです。
WHO は1997年、肥満は「世界的なエピデミック(流行病)」と警告を発しました。WHOによると、世界の成人の肥満人口は1990年と比べると2倍以上に増え、2022年では成人人口の16%にあたる8億9000万人が肥満。
子どもの肥満も同様に増えています。
肥満は社会的要因も大きく、途上国では経済発展で人々の暮らしが豊かになるのに伴い摂取カロリーが増えている半面、仕事や日常生活で体を動かす機会が減っていることが背景です。
一方、先進国では低所得層ほど肥満になりやすい傾向が見られます。低所得層ほど、安価で高カロリーで低栄養価の、いわゆるジャンクフードに日々の食生活を頼らざるを得ないためです。
この傾向は格差の激しい国ほど顕著で、アメリカでは成人の5人に2人が肥満。ただちに治療が必要なBMIが40以上の重度肥満も約1割います。肥満率の高い地域と貧困率の高い地域はかなり重なっています。
日本も貧富の差がどんどん開いているので、食事にはふだんから気を付けなければなりません。