医療用医薬品と一般用医薬品
風邪をひくと、すぐにドラッグストアで風邪薬を買う人がいます。
ドラッグストアなどで販売されている薬は、医師が処方する「医療用医薬品」に対し、「一般用医薬品」と呼ばれています。
一般には「市販薬」と呼ばれることが多いですが、店のカウンター越し(over thecounter = OTC)に販売されることから、「OTC 医薬品」と呼ぶ場合もあります。今回、お話しするのは、一般用医薬品についてです。
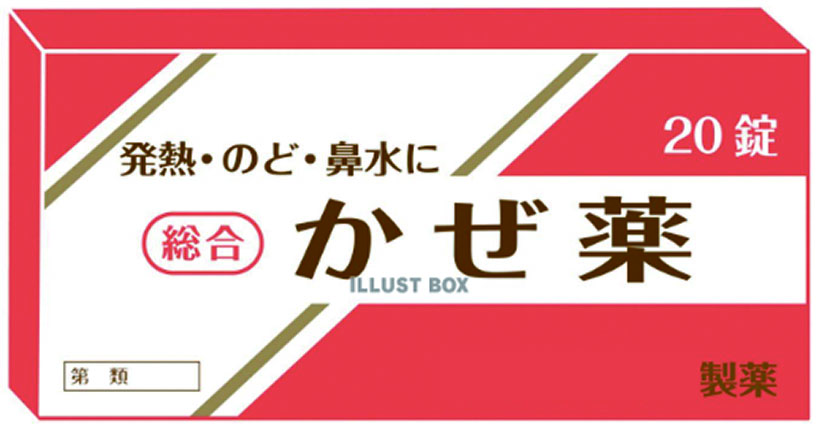
風邪はほとんど自然治癒する
話を風邪に戻します。
風邪は咳、鼻水、熱、頭痛など軽い症状が突然始まり、1週間前後で軽快します。ほとんどがウイルス性で、自然治癒します。まれにゼーゼー、耳の痛み、下痢・腹痛がありますが、これらも自然治癒します。
症状で代表的なのが咳です。咳は異物を排出するための重要な反射反応です。
咳を止めると、痰や異物が出せなくなり、肺炎の原因になることがあります。2~4週間以上咳が続く場合は、咳止めの薬を飲み続けるのではなく、病院で診てもらいましょう。
このように風邪はほとんど自然に治癒するのに、安易に一般用医薬品に頼ると、かえって健康を損ねる場合があります。
以下、なるべく避けたほうがいい一般用医薬品の風邪薬について解説します。
中枢性咳止め薬
咳止めの薬は、中枢性(麻薬系と非麻薬系)と、末梢性とに分けられます。
中枢性咳止め薬は咳反射を抑制します。中枢性咳止め薬に配合されている麻薬系のコデインリン酸塩は、呼吸を抑制し、眠気を引き起こします。18歳未満と妊婦さんは飲んではいけません。
また、ぜんそくの発作やCOPD(慢性閉そく性肺疾患)も使ってはいけません。
気管支のけいれんが起きて、よりひどい咳が出ることもあります。依存性があり、せん妄や腸閉そく、喉頭浮腫による呼吸困難を起こす場合もあります。
せん妄とは、場所や時間を理解する能力が低下し、頭がぼんやりとしている状態で、幻覚や妄想などにとらわれて興奮や錯乱、活動性の低下といった情緒や気分の異常が突然引き起こされる精神障害です。
非麻薬性の中枢性咳止め薬には、デキストロメトルファン(メジコン)やチぺピジンヒベンズ酸塩(アスベリン)などがあり、これらは、呼吸抑制作用があり、慢性の咳には効きません。妊婦さんには禁忌です。のどが渇く、眠気を催す、食欲が落ちる、便秘になるなどの副作用があります。
オーバードースの問題
メジコンは、大量に飲むと麻薬系と似たような精神状況になります。依存性もあります。このため、ドラッグ代わりに乱用(オーバードース)されることがあり、問題になっています。
若者が大量に飲んで、せん妄などになり、救急を受診することがあります。
今年初めには、受験生が受験の不安から大量に服用して救急車で運ばれるというニュースもありました。
服用して車を運転すると交通事故を起こす可能性もあるので、一般用医薬品としては配合を禁止すべき成分です。
風邪薬としての効果も認められないので、本来、一般用医薬品にも医療用医薬品にも使うべき薬ではありません。
抗ヒスタミン薬入り風邪薬
風邪薬には抗ヒスタミン薬が配合されているものもあります。多くの研究論文が、プラセーボ(偽薬)を使った実験結果から、抗ヒスタミン作用のある薬には、風邪を治す効果はないと指摘しています。
クロルフェニラミンマレイン酸塩(ポララミン)が代表的な古くからある抗ヒスタミン薬です。
抗ヒスタミン薬が配合された薬は、緑内障、前立腺肥大症には禁忌です。喘息の発作時や腸閉そくの患者にも使えません。
けいれんや肝障害、異常な興奮を起こすので、子どもには特に危険な薬です。
発熱時に熱性けいれんを起こすことがあるので、一般用医薬品としても医療用医薬品としても使用すべきでない薬です。
副作用は、新薬の開発で徐々に少なくなっていますが、けいれんなどの危険性は ゼロにはなりません。
副作用にけいれんを明示している抗ヒスタミン薬は以下の通りです(カッコ内は商品名)。
クロルフェニラミンマレイン酸塩
シプロへプタジン(ペリアクチン)
クレマスチン(タベジール)
ケトチフェン(ザジテン)
ロラタジン(クラリチン)
デスロラタジン(デザレックス)
ルパタジン(ルパフィン)
セチリジン(ジルテック)
レボセチリジン(ザイザル)
薬害に遭わないために
脳が未熟な3~4歳の子どもや、高齢者は、意識障害を引き起こす可能性のある咳止め薬と抗ヒスタミン薬を配合した風邪薬は、けっして買ってはいけません。
問題は、これら危険な成分が、医療用医薬品にも配合されている場合があることです。病院で処方されても、医者が勧めるのだから安心、とは思わずに、必ず成分を確認しましょう。
当然、そのための最低限の知識も必要になります。










